「生成AIに指示しても期待通りに動かない」「むしろ時間がかかってしまう」…

その焦りや苛立ち、非常によく分かります。
多くの経営者が同じ壁にぶつかっています。しかし、ご安心ください。生成AIが期待外れなのは、あなたのITスキル不足のせいではありません。原因は、生成AIへの「指示の仕方」、つまりプロンプトにある場合がほとんどなのです。
この記事では、なぜ生成AIが思った通りに動かないのか、その根本原因と、今日からできる簡単な解決策の第一歩を、長年WEBと生成AIに携わってきた私の経験から具体的にお伝えします。
「こんなはずでは…」なぜ生成AIは社長の期待に応えられないのか?



佐藤社長、はじめまして。
WEB&生成AIコンサルタントの関俊一です。
さて、早速ですが、生成AIを導入されたものの、期待したような結果が得られず、お困りとのこと、心中お察しいたします。
- 役員会議の資料を作らせようとしても、どうにも抽象的で使い物にならないアウトプットしか出てこない。
- 取引先への大切なメールをお願いしても、あまりに定型的で、心がこもっていないような冷たい文章になってしまう。
- 業界の最新動向をリサーチさせても、情報の出所がはっきりしなかったり、古いデータが混じっていたりして、そのままでは信用できない。
- 新規事業のアイデアを求めても、どこかで聞いたようなありきたりな提案ばかりで、自社の状況や強みを全く考慮してくれない。
「これでは、AIを使うための指示を考える時間ばかりが増えて、かえって非効率じゃないか。」「結局、自分でやり直すことになるなら、最初から自分でやった方が早かった…。」



そう感じていらっしゃるのではないでしょうか?
「こんなはずではなかったのに…」という、そのお気持ち、非常によく分かります。
実は、多くの経営者の方が、AI活用の初期段階で同じような壁にぶつかっているのです。
では、なぜ、高い性能を持つはずの生成AIが、社長の期待に応えてくれないのでしょうか?
その「期待外れ」と感じてしまう状況の根本には、実は、私たち人間側が抱きがちな、生成AIに対するいくつかの「誤解」が存在することが多いのです。
決して、社長のITスキルが不足しているとか、理解力が低いといった問題ではありません。



ご安心ください。
むしろ、生成AIの能力を信じ、期待されているからこそ、そのギャップに戸惑い、無力感のようなものを感じてしまわれるのかもしれませんね。
次のセクションでは、まずその「期待外れ」を引き起こしている、生成AIに対するよくある誤解を一つひとつ解き明かし、社長が生成AIに対して感じていらっしゃる無力感の本当の原因を、一緒に探っていきたいと思います。
生成AIは「魔法の杖」ではない! まず知るべき生成AIとの正しい付き合い方



さて、佐藤社長。
前のセクションでは、生成AIが期待に応えてくれない背景には、我々人間側の「誤解」がある可能性についてお話ししましたね。
その中でも、特に多くの方が陥りやすいのが、「生成AIはまるで魔法の杖のように、いくつかのキーワードを投げ込めば、こちらの意図を汲み取って最適な答えを出してくれるはずだ」という思い込みです。
- 「次期戦略の骨子をまとめて」
- 「取引先へのメールを作成して」
- 「業界動向を調べて」
- 「新規事業のアイデアを出して」
このように、ある程度具体的なキーワードを入れているつもりでも、実は生成AIにとっては、まだ情報が足りないことが多いのです。
なぜなら、生成AIは「空気を読む」ことができません。
社長がどのような状況で、何を目的としてその指示を出しているのか、その背景にある文脈までは自動的に理解してくれないのです。
例えば、「次期戦略の骨子」と言っても、
- どのような会議で使う資料なのか?
- 誰に向けたメッセージなのか?
- どのような時間軸での戦略なのか?
- 重視すべきポイントは何か?(例:売上拡大、コスト削減、新規顧客獲得など)
- 盛り込んでほしい自社の強みや現状の課題は何か?
といった具体的な情報がなければ、生成AIは一般的な、あるいは当たり障りのない答えしか出せないのです。
これは、あたかも非常に優秀だけれども、まだ御社のことをよく知らない新入社員や外部のコンサルタントに、いきなり「よし、戦略まとめておいて」と指示するようなものかもしれません。
彼らも、具体的な背景や条件が分からなければ、的確な仕事はできませんよね。
生成AIもそれと同じなのです。
生成AIは決して万能の「魔法の杖」ではありません。
しかし、だからといって役に立たないわけでは決してありません。
生成AIの能力を最大限に引き出す鍵は、私たち人間側からの「明確で具体的な指示」にあります。
生成AIを、何でも自動でやってくれる魔法使いではなく、指示されたことに対しては驚くほどのスピードと精度で応えてくれる「非常に優秀な相棒」あるいは「頼りになるアシスタント」と考えてみてください。
彼ら(生成AI)がその能力を存分に発揮できるように、必要な情報や条件をきちんと伝えること。
これが、生成AIと上手に付き合っていくための、最も重要で基本的な考え方なのです。
生成AIに対して過度な期待を持つのではなく、しかし、その能力は最大限に活用する。
そのためには、まず「生成AIは指示待ちの存在である」ということをしっかりと認識することがスタートラインとなります。
「とりあえず入力」「コピペで試す」が失敗を招くワケ



佐藤社長、前のセクションではAIを「魔法の杖」ではなく、「指示待ちの優秀な相棒」として捉えることの重要性をお伝えしましたね!
では、その「相棒」である生成AIに対して、私たちは具体的にどのような指示が「失敗」を招きやすいのでしょうか?
社長がお試しになった行動の中にも、実は落とし穴が潜んでいるケースがあります。
例えば、「Webで検索して見つけたプロンプト例をそのままコピー&ペーストして使ってみた」というご経験。
これは、多くの方が最初に試される方法かもしれませんね。
ネット上には確かに、様々なプロンプトのテンプレートや例文が溢れています。
しかし、それらをそのまま使っても、残念ながら「自社の状況に合わない、一般的すぎる回答しか得られなかった」という結果になりがちです。
なぜでしょうか?
それは、Web上で公開されているプロンプト例の多くは、あくまで「不特定多数」に向けた、汎用的なサンプルだからです。
特定の業界、特定の企業、そして社長ご自身が抱える特定の課題や文脈に合わせて作られているわけではありません。
御社には御社ならではの強み、弱み、歴史、文化、そして目指すべき方向性があるはずです。
そうした固有の情報を抜きにして、一般的なプロンプトを投げかけても、AIは御社にとって本当に価値のある、的を射た回答を生成することは難しいのです。
まるで、サイズが全く合わない既製服を着ようとするようなものかもしれません。
また、もう一つのよくある失敗例として、「とりあえず思いついた単語をいくつか入力して、生成AIに要約やアイデア出しをさせてみた」というケースがありますね。
例えば、「次期戦略」「コスト削減」「新規事業」といったキーワードだけをポンと入力する。
これでは、生成AIは何をどうすれば良いのか、ほとんど理解できません。
前のセクションでお話ししたように、生成AIは文脈を読み取ることができないからです。
- 「どの製品についての戦略なのか?」
- 「どの部門のコストを削減したいのか?」
- 「どんな分野での新規事業をイメージしているのか?」
- 「誰に向けたアイデアが必要なのか?」
こうした具体的な背景情報が全くない状態で単語だけを与えられても、生成AIは推測するしかありません。
その結果、「意図が全く伝わらず、的外れな回答や、意味不明な文章が出力された」という事態を招いてしまうのです。
これでは、修正する方がかえって時間がかかり、「使えない」と感じてしまうのも無理はありません。
こうした「とりあえず」や「コピペ」による失敗体験が積み重なると、「生成AIなんて、結局使えないじゃないか」という結論に至ってしまいがちです。



しかし、それはAIの能力の問題ではなく、あくまで「指示の仕方」の問題なのです。
生成AIが社長の意図を正確に理解し、期待に応えるためには、これらの方法では情報が圧倒的に不足している、ということをまずご理解いただければと思います。
焦りや恥ずかしさを解消! AIを「頼れる右腕」に変える意識改革
佐藤社長、AIが期待通りに動かない状況が続くと、「周りの経営者はもっとうまく活用しているのではないか…」とか、「今さら社員に基本的なことを聞くのは恥ずかしい…」といった焦りや、少しばかりの気まずさを感じてしまわれるかもしれませんね。
特に、社長というお立場上、「知らない」「できない」という姿を見せることへの抵抗感があるのは、当然のことだと思います。



しかし、社長!
その焦りやプライドが、かえってAIという強力なツールの活用を妨げ、問題解決を遠ざけてしまっている可能性があるとしたら、どうでしょうか?
まず、何よりもお伝えしたいのは、生成AIを現時点で完璧に使いこなせていないことは、決して恥ずかしいことではないということです。
生成AIは比較的新しい技術であり、多くの人が試行錯誤している段階なのですから。
そして、ここが非常に重要なポイントなのですが、生成AI活用で本当に大切なのは、生成AIを巧みに操作する「スキル」そのものよりも、生成AIに何を、どのように「依頼」するかを明確にする「思考」の方なのです。



考えてみてください。
社長が優秀な部下や秘書の方に仕事を依頼する時、漠然とした指示ではなく、目的や背景、期待する成果物、必要な情報などを具体的にお伝えになりますよね?
生成AIとの関係も、それに近いものだと捉えてみてはいかがでしょうか?
生成AIを、得体の知れない難解なテクノロジーとしてではなく、社長の指示を忠実に、そして迅速に実行しようと待っている「非常に有能な、しかし指示待ちの部下」あるいは「頼りになる右腕となる可能性を秘めた秘書」のように考えてみるのです。
彼ら(生成AI)が最高のパフォーマンスを発揮できるように、社長の「思考」を整理し、それを明確な「指示」として伝える。
この意識改革こそが、生成AIに対する苦手意識や焦りを解消し、生成AIを真に「使える」ツールへと変える鍵となります。
ITスキルに自信がないと感じていらっしゃるかもしれませんが、心配はいりません。
社長がお持ちの経営者としての経験知、課題認識、そして実現したいことへの明確なビジョン、それらを生成AIに伝えるための「思考」こそが、他の誰にも真似できない、社長ならではの生成AI活用を可能にするのです。
生成AIを操作する技術的な側面は、基本的なことを押さえれば十分です。
それよりも、生成AIという「右腕」に、どのような「仕事」を、どのような「意図」で任せるか。
そこに意識を集中させることが、生成AI活用の第一歩であり、最も重要な核心部分なのです。
今日からAIの応答が変わる! まず試したい「たった一つのコツ」



佐藤社長、生成AI活用の鍵が「スキル」よりも「思考」にあり、AIを「頼れる右腕」と捉える意識改革が重要である、というお話をしてきましたね!
では、その「右腕」である生成AIに、社長の思考を効果的に伝え、期待通りの働きをしてもらうために、今日からすぐに試せる、具体的で簡単な「たった一つのコツ」をお伝えしましょう。
それは、生成AIに指示を出す際に、「まず最初に、生成AIに『役割』を与える」ということです。
たったこれだけ?
と思われるかもしれません。
しかし、この一手間が、生成AIの応答を劇的に変えることになるのです。
なぜ『役割』を与えることがそんなに重要なのでしょうか?



思い出してください。
生成AIは「指示待ちの優秀な相棒」であり、「空気を読む」ことはできませんでしたよね。
何の役割も与えられずに、ただ「資料をまとめて」「メールを書いて」と指示されると、生成AIはどのような立場や視点で、どのレベル感で応答すれば良いのか、判断が難しいのです。
これは、社長が部下に仕事を指示する場面を想像していただくと分かりやすいかもしれません。
例えば、単に「市場調査をしてくれ」と指示するよりも、「君はマーケティング部の担当者として、新規顧客開拓のための市場調査をして、来週の会議で発表できる形でレポートをまとめてくれ」と指示した方が、部下はより的確に動けますよね。
どの部署の、どのような目的のための調査で、アウトプットの形式は何なのか、が明確になるからです。



生成AIも同じです。
最初に「あなたは経験豊富な経営コンサルタントです」「あなたは優秀なコピーライターです」「あなたは製造業に詳しいアナリストです」といった役割を与えることで、生成AIはその役割になりきり、より専門的で、文脈に沿った応答を生成しやすくなるのです。
例えば、これまで「次期戦略の骨子をまとめて」という指示で、抽象的な答えしか返ってこなかった場合。
これを、
「あなたは中小製造業の経営戦略に詳しいコンサルタントです。
当社の強みである[具体的な強み]を活かし、今後3年間で売上を20%向上させるための次期戦略の骨子を、役員会議で説明することを想定して3つのポイントでまとめてください。」
このように、最初に役割を与え、続けて目的や条件を具体的に伝えることで、AIの応答の質は格段に向上するはずです。
あるいは、取引先へのメール作成で「定型的で冷たい文章」になってしまう場合も、
「あなたは丁寧で誠実な営業担当者です。
長年お付き合いのある[取引先名]の[担当者名]様へ、[用件]について感謝の気持ちを込めたメールを作成してください。」
と役割設定をすることで、生成AIはより人間味のある、適切なトーンの文章を生成しやすくなります。



難しく考える必要はありません。
まずはどんな簡単な指示でも構いませんので、生成AIに話しかける最初の“枕詞”として、「あなたは〇〇です。」と役割を与えてみることから始めてみてください。
この「たった一つのコツ」が、社長と生成AIの関係を、より生産的なものへと変える第一歩となるはずです。
本編に続く…
まとめ
さて、この先は電子書籍の本編をご覧いただければと思います。
まとめの前までは、Gemini2.5がチェーンプロンプトという技術を使って書きました。また、構成されている6つのプロンプトは弊社で制作しています。
しかも、まとめの前までリライトは装飾を入れている以外全くありません。
これくらい生成AIを使いこなせるとあなたの業務のどれくらいが効率化できるでしょうか?
何もそれは効率化をしよう。とだけ言っているのではありません。
効率化するところは効率化して、もっと大切なことに時間を使いましょう。ということが言いたいだけなんです。
タスクの管理や繰り返し業務はある程度生成AIに任せて、本来やるべき社長の大切な仕事をしませんか?というご提案です。
生成AIの時代は色々なことが今までよりパーソナライズされていくと思うんです。
例えば、弊社が現在進めているのは、手書きのニュースレターを作っています。やはり今でも効果が高いですし、どんどん生成AIによって無機質な方向に進む中で、手書きのニュースレターが来たらいかがでしょうか?
ご自身が受け取ったことをイメージしていただければおわかりいただけるのではないでしょうか?
そのためにも、生成AIを使いこなすことが鍵になってくると思います。
弊社が提供する生成AIのこちらの講座が今なら無料です。
興味がある方はぜひご参加くださいね!
また、有料講座では、指示の出し方や色々な生成AIの講座もご用意していますので、興味がある方はぜひご参加ください。
また、参考までに、この登場人物の佐藤社長のペルソナは以下のような設定がされています。
もちろんこれも全てではありませんが、生成AIに手伝っていただいています。
佐藤社長のペルソナ
名前: 佐藤 健一 (さとう けんいち)
職業: 中小企業(従業員30名程度の製造業)の社長(2代目)
性別: 男性
居住地: 神奈川県横浜市
家族構成: 妻、子供2人(高校生、中学生)
佐藤 健一 の年齢:52歳
佐藤 健一 の性格:
- 責任感が強く、真面目で社員想い。会社の将来を常に案じている。
- 新しい情報や技術動向にはアンテナを張っているが、実践には慎重。
- 社長としてのプライドが高く、人に弱み(特に「知らないこと」)を見せられない。
- 決断は早いが、根本的な課題解決よりも目先の業務に追われがち。
- 効率化への関心は高いが、ITツールへの苦手意識が少しある。
佐藤 健一 の対象の悩み:
- 生成AIを業務(資料作成、メール、情報収集、アイデア出し)に活用したいが、的確な指示(プロンプト)ができず、期待通りに動いてくれない。むしろ時間が増えている。
- 周囲の経営者仲間が生成AIを活用している話を聞き、自社だけが取り残されているのではないかと強い焦りを感じている。
- 有料の生成AIツールを契約したが、結局使いこなせず費用が無駄になったと感じ、自己嫌悪に陥っている。
- 社員(特に若手)に生成AIの使い方を聞きたいが、「社長なのに知らないのか」と思われるのが怖くて聞けない。
- 「生成AIは魔法の杖ではない」と頭では理解しつつも、なぜ上手くいかないのか、具体的にどうすれば良いのか分からず途方に暮れている。
佐藤 健一 の興味・関心:
- 自社製造ラインの生産性向上とコスト削減策。
- 競合他社のDX(デジタルトランスフォーメーション)の具体的な取り組み事例。
- 中小企業でも導入しやすい実践的な業務効率化ツールや手法。
- 経験豊富な社員のノウハウを若手に継承する方法。
- 経営者としての自己成長、リーダーシップ論。
- (個人的な関心)健康維持のための情報、週末のゴルフ。
佐藤 健一 の特徴的な行動:
- 毎朝、経済ニュースや業界ニュースサイトで「AI」「DX」関連の見出しをチェックする。
- Web検索で見つけた「社長のための生成AI活用プロンプト集」などを試すが、自社の状況に合わず断念する。
- 会議で部下に「生成AIを使って何か新しい提案を考えてみてくれ」と漠然と指示を出す。
- 経営者向けの生成AI活用セミナーの案内メールは開くが、「時間が取れない」「難しそう」と感じて申し込まないことが多い。
- 夜、一人でオフィスに残り、生成AIツールを開いて色々な指示を試すが、結局うまくいかず、苛立ちながらPCを閉じる。
以上
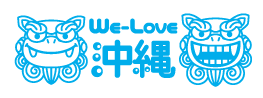
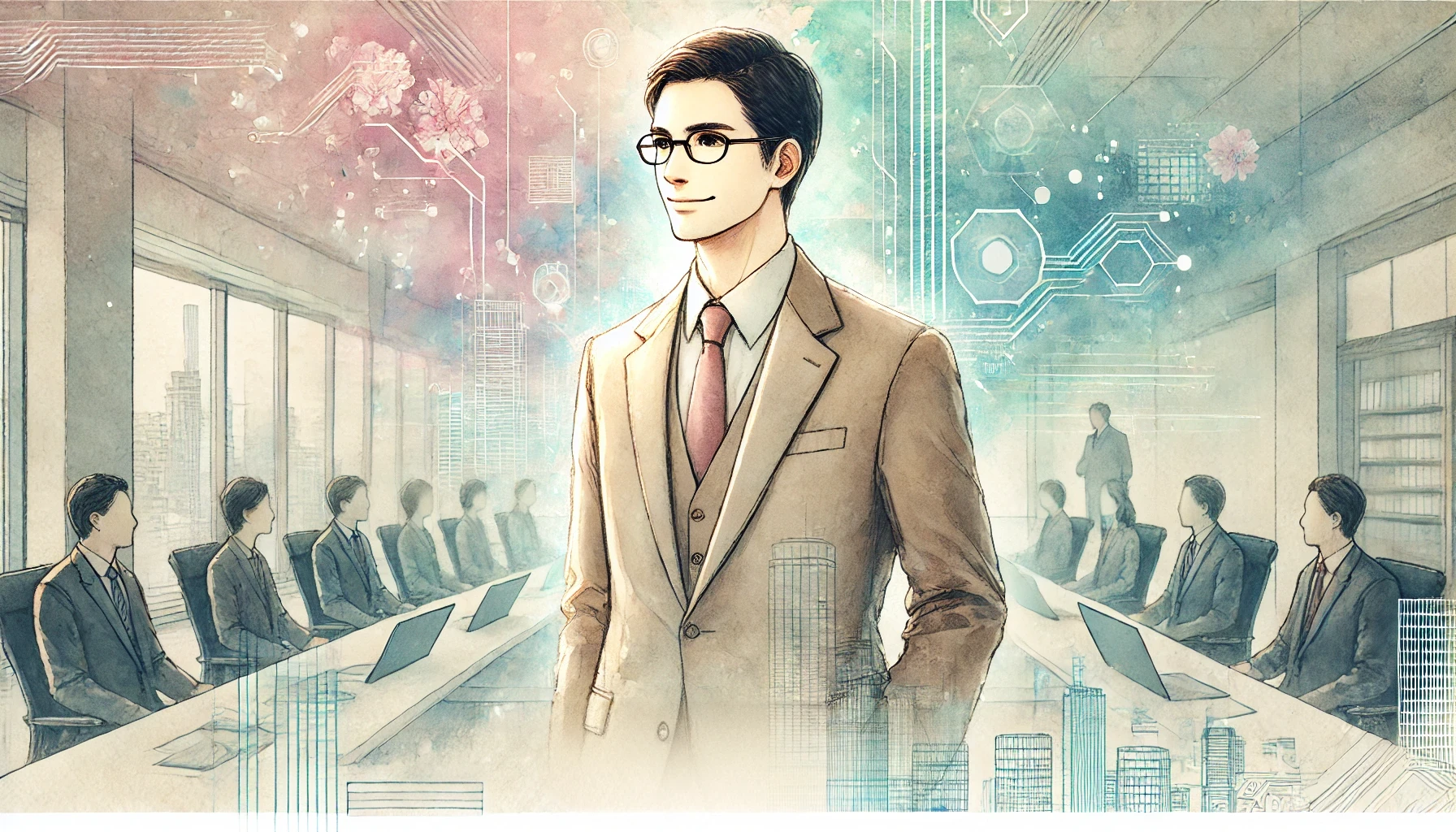


コメント